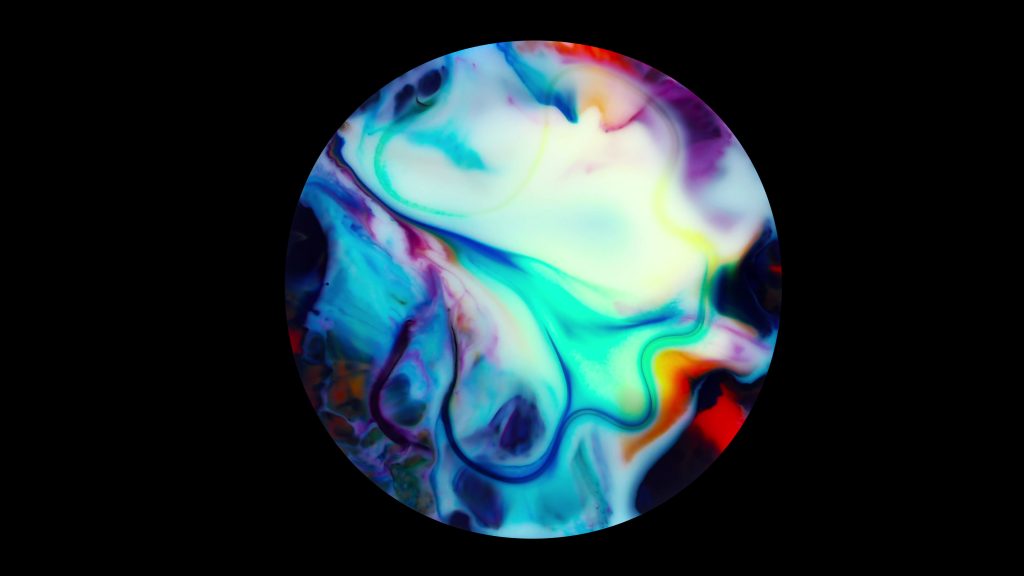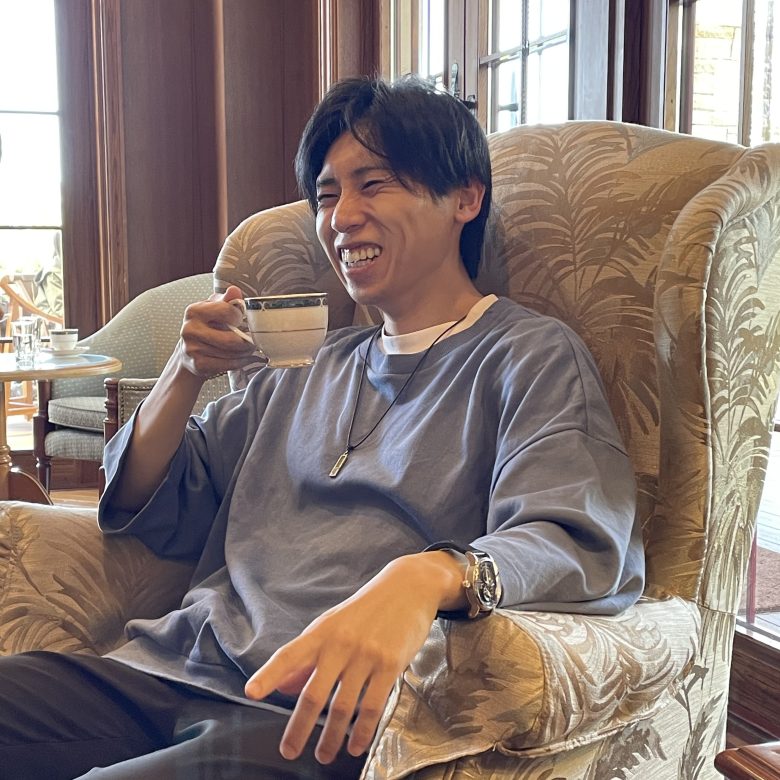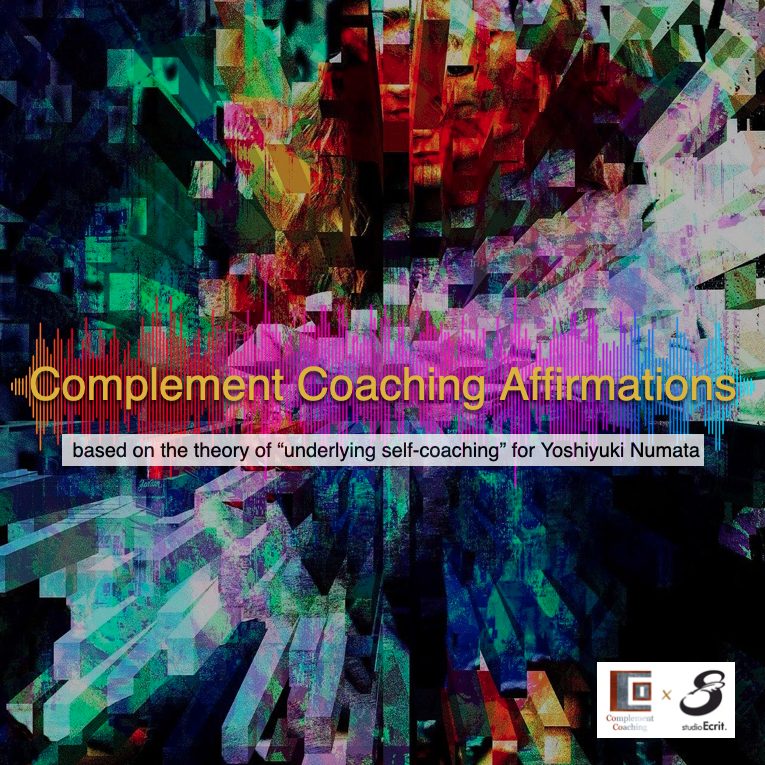生産性とは「投入した資源に対して得られた成果の量を示す指標」の事を言います。生産性は、この資源を減らし、成果の量を増やすことで高めることが可能です。故に、最小資源で最大成果を出すことで生産性は高まります。また、ここでいう資源とは、時間や金銭など成果を得るために費やしたコストのことで、成果とは新たに得る資源のことを言います。つまり「どれだけの資源を投入してどれだけの資源が返ってくるか」によって生産性の値が決まります。
資源(Resource)を$R $とすると以下の関数で表せます。ここで、$r_i $は「資源の各要素(時間や金銭など)」を表します。とりあえず6個の要素をあげていますが、それ以外はまとめて「その他の資源$n $」としています。$ w_i $は「それぞれの要素に対する重み」であり、この重みは個人や状況によって変化します。
\[R=\sum_{i} w_i r_i = w_p p + w_t t + w_m m + w_f f + w_s s + w_o o + w_n n \]
資源の各要素
• 身体的リソース $p$(労働による疲労、体力消耗)
• 時間的リソース $t$(作業や学習に費やす時間)
• 精神的リソース $m$(ストレス、集中力の消耗)
• 金銭的リソース $f$(コスト、投資)
• 社会的関係リソース $s$(社会的地位や人脈の活用コスト)
• 機会費用 $o$(他の選択肢を捨てるコスト)
•その他の資源 $n$
このように数式化することで、様々なことがわかります。例えば、ある選択に投入した資源を$R_1 $、返ってくる資源(成果)を$R_2 $とした時、$R_2 - R_1 > 0 $の場合は、プラスの生産性となり、その方法を繰り返し選択するほど手持ちの資源が総合的に増えます。逆に$R_2 - R_1 < 0 $の場合は、マイナスの生産性となり、その方法を繰り返し選択するほど手持ちの資源が総合的に減ります。また、この生産性の考えは、あらゆる資源に当てはまることがわかります。例えば精神的リソース$m $以外の要素$p,t,f,s,o,n $の値を$0 $として考えた時、$R_2 - R_1 > 0 $という式(プラスの生産性)が当てはまる方法を繰り返し選択することで、精神をプラス(健康)にし、ストレスを軽減したり集中力を温存したりできると考えられます。「生産性」と聞くと「どれだけ社会にモノや価値を生み出したか」といったGDP(国内総生産)的な成果イメージが浮かぶかと思いますが、上記の関数に基づくと、生産性の向上によって効率よく得られる成果物は多種多様です。
上記の関数から生産性を高めることで様々な成果を得られることがわかりますが、これはあくまでも費やした資源に対して効率よく成果を得るための方を法示したものであり、実際に「成果量を増やす」には別の関数が必要です。その関数は以下の式で表せます。
限定記事「お金のゴールを達成する方法」は、パーソナルコーチングもしくはスキャルピングトレードコンサル×パーソナルコーチングを受けられた方限定に公開しています。パスワードを入力することで閲覧可能になります。