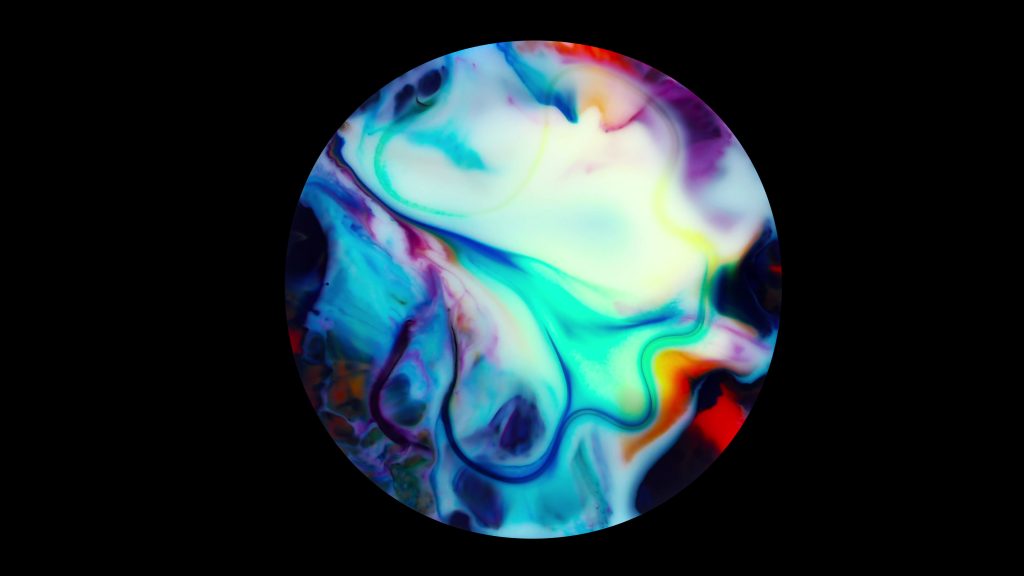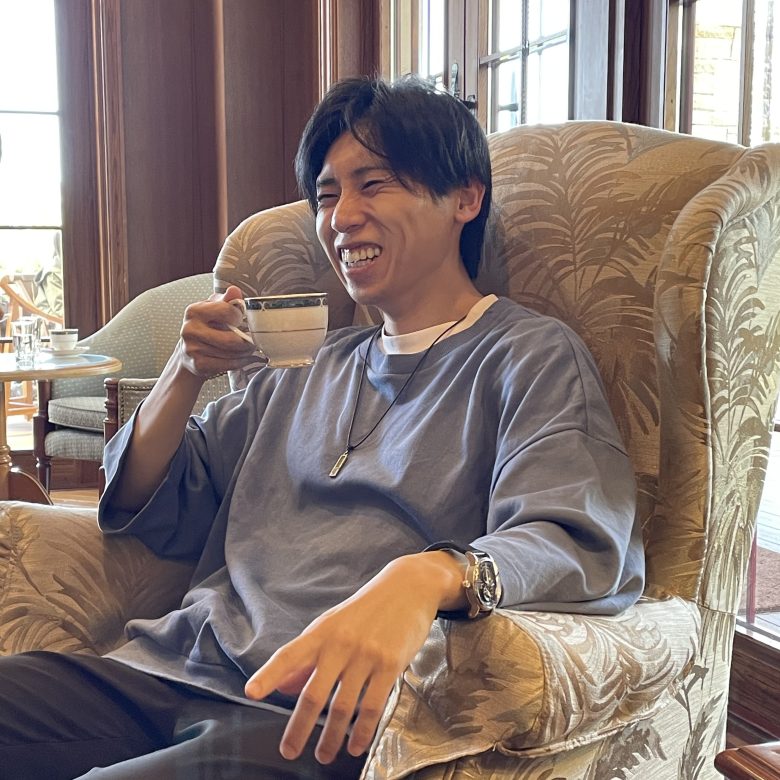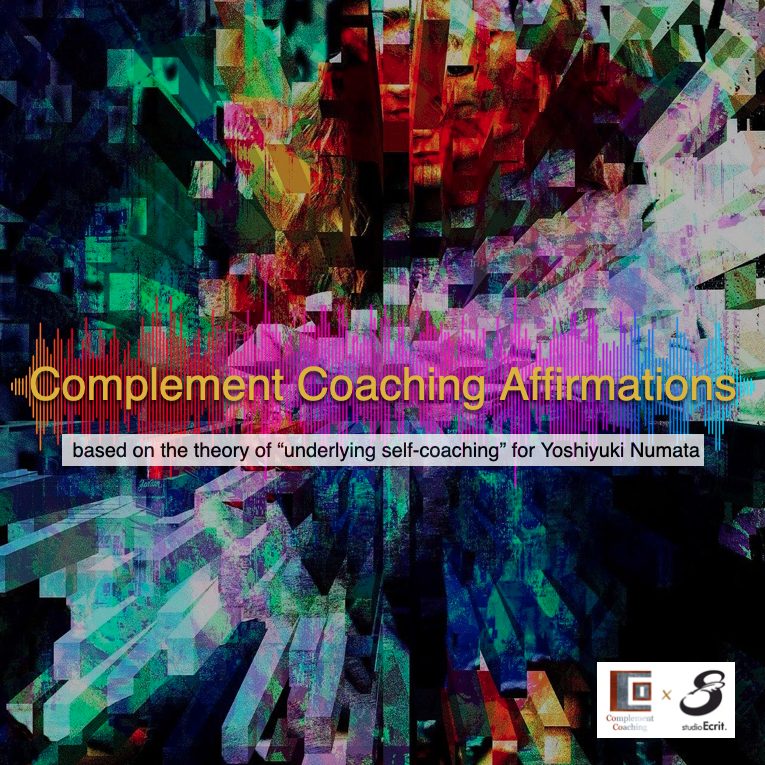自然数論のシステムでは$ 1+1=2 $ですが、お金のシステムでは$1+1=5$になることもあれば$1+1=0$になることもあります。例えば、700円の蕎麦に20円の大根おろしを添えるだけで「800円のおろし蕎麦」に化けます。逆に、800万円の新車のベンツを40万円かけて全塗装した結果「700万円の特殊な色のベンツ」に化けることもあります。このように、自然数論のシステムであれば$700+20=720$のはずですが、お金のシステムでは$700+20=800$になるといったことが当然のように起きているのです。
人間は情報をただの数量として認識するのではなく、複雑なゲシュタルトを形成して「意味」で理解します。例えば、蕎麦と大根おろしが一緒になると「おろし蕎麦」という新たな「ゲシュタルト」が生まれます。このゲシュタルトはバラバラに捉えている時とは異なる意味を持ちます。そして「一つ一つ個別の状態」と「一つのまとまりとしての全体性のある状態」それぞれに異なる意味があり、その意味は価値(値段)に反映されます。つまり情報は組み合わせによって、それぞれ決まった価値を持つのです。
お金のシステムで、自然数論のような「絶対的な数量体系」が機能しないのは、人間の価値認知が「主観的」かつ「文脈依存的」な側面を持つからです。つまり、お金のシステムは「人間の価値判断に依存し、文脈によって動的に変わるもの」だということです。お金は「数値」で表されているにもかかわらず、その実体は単なる「数量」ではなく「価値認知」です。したがって、お金は数学的に扱うべき事柄というよりは、認知科学的・言語学的に人の価値認知(意味付け方法)に基づいて扱われるべき事柄であると言えます。お金と価値の関係は、言語学の意味論の観点から捉えることで理解しやすくなります。以下、3つの意味論の観点から「お金と価値の関係」について記述します。
限定記事「お金のゴールを達成する方法」は、パーソナルコーチングもしくはスキャルピングトレードコンサル×パーソナルコーチングを受けられた方限定に公開しています。パスワードを入力することで閲覧可能になります。